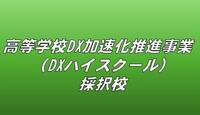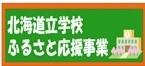カテゴリ:酪農科学科
とかちプラザまつりに参加しました
9月6日(土)~7日(日)、酪農科学科養豚分会はとかちプラザまつりに参加しました。アニマルウェルフェア畜産協会とコラボし、環境に優しい畜産についてPR。本校で育てた豚の革を使ったキーホルダー作りのワークショップも開催し、多くの方に畜産の飼育環境に関心を持ってもらう機会となりました。
帯広の森幼稚園と動物ふれあい体験を実施しました
9月3日(水)、酪農科学科では3年生が帯広の森幼稚園の園児たちに動物ふれあい体験を実施しました。乳牛・豚・馬といったさまざまな家畜に触れ、えさやりや馬とのふれあいなど体験学習も行いました。中でも幼稚園で自ら育てたにんじんを持参し、馬に食べさせる様子はとても楽しそうで、子どもたちからも「にんじん食べてくれて嬉しかった!」「牛さん可愛い!」といった声があがり、楽しい体験の時間になりました。
雪印メグミルクチーズセミナー
9月1日(月)、酪農科学科3年生の授業で雪印メグミルクによるチーズセミナーを実施しました。チーズの歴史や、種類について学ぶとともに雪印メグミルクで製造されている多様なチーズについて試食し、風味や食感などの違いについて学びました。ブルーチーズや羊のチーズなど普段食べることのないチーズも含めた6種類を試食し、チーズという製品の奥深さについて理解を深める機会となりました。
第34回北海道肉用牛共進会で奨励賞受賞!
8月29日(金)~30日(土)、酪農科学科の生徒が第34回北海道肉用牛共進会に本校で飼養する黒毛和牛1頭を出品しました。北海道全域から優れた肉用牛が出品されるなか、本校で飼養する「まりん」号が、高校・大学等の教育機関が出品している肉用牛の中でハンドラーの技術を含め最も高く評価され、見事奨励賞に選ばれました!第5区の出品区分でも1等5席と上位入賞に食い込むことができ、さらなるステップアップを感じられる結果となりました。目標は2年後に行われる全国和牛能力共進会北海道大会への出場!より高みを目指して和牛生産に取り組んでいきます!
酪農科学科1学年農事見学に行きました。
8月29日(金)、酪農科学科1年生は、鹿追町のカントリーファーマーズ藤田牧場様、よつ葉乳業十勝主幹工場様、ホクレン帯広支所十勝地区家畜市場様の農事見学を実施しました。畜産の生産から加工、流通に関わる施設を見学することができました。この学びを活かして、今後の専門学習に取り組んでいきます。
酪農科学科・夏季国内委託実習が始まりました。
8月10日(日)、酪農科学科2年生の1名が国内委託実習を芽室町の株式会社大野ファームで開始しました。夏季休業期間中に最大7日間の実習を行う国内委託実習に参加した生徒は他の生徒より多く単位認定されるため、自分自身で目的を持って取り組み、終了後には学科内で研修報告をするようにしています。多くの学びの得られる機会であり、実習にご協力いただきました、株式会社大野ファーム様、誠にありがとうございました。
酪農科学科・乳牛分会 北海道の暑さもこれで乗り切れるか!?
7月22日(火)、酪農科学科2年・乳牛分会がプロジェクト活動の一環で取り組む林間放牧を開始しました。24日に38.8℃を記録するほどの暑さとなった帯広ですが、暑熱ストレスを緩和する林間放牧に、乳牛たちはすごくのんびりと過ごしている様子が見られます。健康面での影響だけでなく、環境要素の比較検証など様々な角度から林間放牧について検証を行っていきたいと思います!
コラボパン販売会を行いました。
7月19日(土)、酪農科学科養豚分会と食品科学科肉加工分会は、満寿屋商店ボヌールマスヤ店様とのコラボパン「帯農黒豚ウインナーのうまみたっぷりピザパン」「帯農黒豚ウインナーのふわもちちぎりパン」の販売会を行いました。生産した豚を自分たちの手で加工し、商品となり消費者に届くまでを見届けることができ大変貴重な経験となりました。
令和7年度 第3学年酪農科学科 農事見学
7月17日(木)~18日(金)、酪農科学科3年生は、道東方面で1日目は中標津町の竹下牧場様、岩谷学園ひがし北海道IT専門学校様での視察研修。2日目は津別町のエゾウィン株式会社様、中標津町の道総研酪農試験場、釧路市の猛禽類医学研究所での視察を実施しました。企業や生産者の方々から、スマート農業に関連することを丁寧に説明していただき、貴重な時間となりました。
十勝和牛振興協議会より基金をいただきました
7月11日(金)、十勝総合畜産共進会〔肉牛の部〕にて本校の和牛クラブに十勝和牛振興協議会より担い手を支援する目的で創設された基金から支援金・高能力雌牛の凍結受精卵をいただくことになりました。全国和牛能力共進会に向けて、和牛生産に取り組む、帯広農業高校・更別農業高校・北海道立農業大学校へのご支援に大変感謝いたします。生徒たちは宮前会長にお礼の言葉をお伝えし、このご支援を大切に活用しながら優秀な和牛の生産に取り組んでいきたいと思います。
十勝総合畜産共進会〔肉用牛の部〕で上位入賞!
7月10日(木)~11日(金)、酪農科学科の生徒が十勝総合畜産共進会〔肉牛の部〕に本校で飼養する黒毛和牛2頭を出品しました。結果25部で1等賞4席、26部で1等賞7席を獲得することができました。本校としても初めてレベルの高い十勝で上位入賞に食い込むことができましたが、優等賞には及ばずプロの畜産農家の技術力が大変大きな学びとなりました。参加した生徒たちも非常に勉強になった様子であり、8月の全道大会に向けて一層の牛づくりに励んでいきたいと思います。
豚の行動観察試験事前学習会を行いました。
7月1日(火)、酪農科学科養豚分会は帯広畜産大学の瀬尾哲也准教授をお招きして、行動観察試験のレクチャーを受けました。養豚分会では、アニマルウェルフェアに配慮した飼育を実践しています。豚本来の行動が発現できているか根拠あるデータを蓄積し、発信活動へ繋げていきたいと考えています。
酪農科学科・乳牛分会 林間放牧に挑戦中!
7月1日(火)、酪農科学科2年・乳牛分会は林間放牧に向けた準備を進めています。北海道も猛暑の続く日が増えており、乳牛には厳しい日々が続いています。そんな中で暑熱ストレスを緩和する取り組みとして林間放牧が注目されており、乳牛分会でも試験的に挑戦しています。草架台を設置する場所の下草刈りを行い、林間放牧に向けた準備を着実に進めています。
豚革製品の販売活動を行いました
6月27日(金)、酪農科学科養豚分会はアグリスで豚革製品の販売活動を行いました。本校で生産した豚の革で、豚革製品を作製しています。プロジェクト活動ではアニマルウェルフェアを軸に、豚の本来の行動発現ができるような飼育環境になるよう工夫を凝らしています。消費者の方へ発信し、理解を深める活動に展開します。
酪農科学科・第2回新規就農プログラム講演会
6月26日(木)、酪農科学科では新規就農プログラム研究開発の一環として第2回講演会を実施しました。非農家出身でありながら、富山県で第三者継承により就農したClover Farmの青沼 光さんにご来校いただき、貴重な講演会の実施となりました。将来、新規就農を目指している生徒からは、新規就農へとつながった具体的な道筋やこれから就農を目指すにあたって、どのように方向を目指すべきかをお話しいただきました。夢の実現に向けて、自分たちの想いをより一層大きく膨らませる素晴らしい機会となりました。
令和7年度 校内家畜審査競技会(乳用牛の部)
6月24日(火)、酪農科学科は外部審査員として上士幌町の小椋淳一様をお招きし、令和7年度校内家畜審査競技会(乳用牛の部)を開催しました。経産牛・未経産牛の部に分かれ、生徒たちは真剣な眼差しで審査に励んでいました。審査講評の際には生徒からの質問に丁寧に受け答えしていただき、学びの深い内容となりました。上位入賞者は8月7日~8日に岩見沢市で開催される全道技術競技大会へ出場します。知識を審査で見極める力量を高め上位を目指してほしいと思います。
酪農科学科3年・削蹄講習会
6月23日(月)、酪農科学科3年生が削蹄講習会を行いました。株式会社THA BOSの右谷様を講師にお迎えし、油圧式削蹄枠での削蹄の様子を見学・体験させていただきました。本校は削蹄実習を行っていますが、削蹄師による全頭削蹄を年1回行って降ります。生徒たちもプロの技術を学ぶため、積極的に質問するなど学びを深めていました。削蹄師による素早い作業と正確な技術に生徒たちも大きな学びを得ることができました。
満寿屋商店様とのコラボパン開発に向けた意見交流会を行いました
6月11日(水)、食品科学科肉加工分会と酪農科学科養豚分会は、満寿屋商店様とのコラボパン開発に向けた意見交流会を実施しました。この取り組みでは、満寿屋商店様の食パンの耳を飼料として育てた豚を本校でウインナーに加工。このウインナーをメインにしたコラボパンを開発し、多くの消費者の皆様にお届けしたいと考えています。
とかち大平原交流フェスタに参加しました
6月8日(日)、農業科学科小麦分会と、酪農科学科養豚分会はとかち大平原交流フェスタに参加しました。小麦分会は農業にまつわる丸バツクイズ大会を実施し、大いに盛り上がりました。養豚分会は、本校で育てた豚の革を使いワークショップを行いました。家族連れで楽しみながら、畜産の飼育環境に興味を持っていただけるきっかけになったと思います。
第二ひまわり幼稚園への酪農教育ファーム活動
6月11日(火)、酪農科学科では第二ひまわり幼稚園の園児たちに、酪農教育ファーム活動を実施しました。乳牛を通じて酪農について知ってもらうための取り組みであり、牛に関するクイズや餌やり、ブラッシング体験で乳牛にとふれ合いました。トラクターへの乗車体験なども行い、子どもたちからは「かわいい」「触ると気持ちいい」などの声も聞かれました。秋には哺乳・搾乳体験をやる予定で、酪農の魅力を伝えていきたいと思います。
酪農科学科・草地更新圃場の飼料作物現地講習会
6月10日(火)、酪農科学科2・3年生が昨年度草地更新を行った本校の飼料作物圃場にて現地講習会を実施いたしました。(独)家畜改良センター十勝牧場より塩沢様・曽和様をお迎えし、北海道優良品種である、チモシーの「なつぴりか」「なつさかり」を播種した更新圃場の植生調査から優良品種の特性等について学びました。来週には収穫作業も始まります。収量調査なども進めながら飼料作物への学びを更に深めていきたいと思います。
第2回帯広市総合畜産共進会〔肉用牛の部〕
6月5日(木)、酪農科学科和牛クラブの生徒が第2回帯広市総合畜産共進会〔肉牛の部〕に本校で飼養する黒毛和牛2頭を出品しました。今年度最初の共進会出品でしたので生徒たちも不安な気持ちを抱えながらの参加でした。今回は1部・黒毛和種 9ヶ月以上12ヶ月未満の部に出品しました。停姿勢や牛の見せ方にまだまだ課題があったものの、出品の結果としては4頭の出品牛の中から1位と2位に見事選んでいただきました。7月の十勝、8月の全道共進会に向けて多くの関係者よりご助言をいただき、さらなるレベルアップが目指せると確認できた大会でした。今後に向けてより一層励んでいきたいと思います。
第2回帯広市総合畜産共進会〔乳用牛の部〕
6月5日(木)、酪農科学科ホルスタインクラブの生徒が第2回帯広市総合畜産共進会〔乳用牛の部〕に5頭を出品しました。第3部当才ミドルクラス〔12ヶ月~15ヶ月未満〕の部では『カチノー グランシヤール ユナイテッド』号が1位、『カチノー OK ドール S キツク ライオネル』号が3位に選ばれるなど素晴らしい成果を上げることができました。今年は第16回全日本ホルスタイン共進会が開催される年であり、出場に向けてホルスタインクラブとしても例年以上に気合いが入っています。そのような中でこのように評価していただけたことはものすごいモチベーションにもなります。9月の十勝総合畜産共進会に向けて更にレベルアップできるように励んでいきたいと思います。
2025北海道ブラックアンドホワイトショウ
5月23日(金)~25日(日)、安平町の北海道ホルスタイン共進会場で開催された2025北海道ブラックアンドホワイトショウに本校ホルスタインクラブが参加しました。現在本校で飼養管理をしている『ケニフロウ トウービーフエイマス ネツト』号がジャージー種の部 [リザーブ・ジュニア・チャンピオン]に選ばれたほか、リードマンコンテストにおいても本校の生徒が多く上位に選ばれるなど、技術の向上も見られた大会となりました。10月に開催される全日本ホルスタイン共進会に向けて、より高みを目指す飼養管理に励んでいきたいと思います。
本校の生徒の様子が番組放送(STV)で紹介されました!
5月31日(土)放送(STV)
「どさんこワイド179スペシャル ミライをつくる高校生 農業高校でいのちを学ぶ」の中で本校酪農科学科の生徒の様子が特集されました。どさんこワイド179の公式YouTubeチャンネルで見ることができます!
皆さん、ぜひご覧ください!
https://www.youtube.com/watch?v=cRKucQGWRrg
酪農科学科、動物ふれあい体験〔第一いずみ幼稚園来校〕
5月29日(木)、酪農科学科3年生は第一いずみ幼稚園の園児と動物ふれあい体験を行いました。今年度は馬インフルエンザの影響で残念ながら馬との交流活動ができませんでしたが、乳牛・肉牛・豚といった様々な家畜とふれあってもらい、餌やりやブラッシングを体験してもらいました。子どもたちからは「かわいい!」「草食べてる!」などの楽しそうな声が溢れていました。
酪農科学科・和牛受精卵の採卵・移植技術講習会
5月27日(火)、酪農科学科2年生が和牛受精卵の採卵・移植技術を学ぶ講習会を行いました。とかち繁殖技術研究所の松崎様を講師にお迎えし、採卵プログラムで準備を進めてきた和牛2頭から採卵を実施していただきました。採卵した受精卵は選別後、そのまま乳用牛に移植されました。生徒たちは動物バイオテクノロジー分野の技術を間近で学ぶことができ、貴重な経験となりました。
第54回十勝ブラックアンドホワイトショウ
5月17日(土)、ホルスタインクラブは音更町で開催された第54回十勝B&Wショウに経産牛2頭、未経産牛3頭の出品とリードマンコンテストに参加してきました。結果は実らない部分もありましたが、リード技術や毛刈りの技術は格段と進歩していると実感することができました。今週末も全道共進会があるため、チーム一丸となって頑張っていきます。
酪農科学科・乳牛分会のプロジェクト活動
5月13日(火)、2年生乳牛分会では林間放牧の実践に向けた倒木の撤去作業を行いました。今年度も少しずつ暑くなってきています。酷暑が予想される夏に向けてプロジェクト活動では森林を活用した放牧にチャレンジします。暑熱ストレス対策は現在の北海道酪農においても大きな課題でありこの課題解決型学習で成果を出せるように頑張っていきたいと思います。
デントコーンの播種作業が始まりました
5月7日(水)、酪農科学科では本校実習圃場でデントコーンの播種作業が始まりました。デントコーン栽培は、長年、ホクレン・畜産試験場と連携した栽培試験を実施しています。播種作業は北海道クボタ様の真空播種機で行われました。また、今年度は作業効率化を記録するため「レポサク」を導入し、労働生産性の調査も実施しています。生徒たちも普段とは異なる作業機や機器を用いた播種作業にとても興味を示していました。今後生育調査を実施しながら秋の収穫に向けて管理作業を続けていきたいと思います。
第51回南十勝ブラックアンドホワイトショウ
4月25日(金)、ホルスタインクラブは大樹町で開催された第51回南十勝B&Wショウに育成シニアクラスに2頭、4歳クラスに1頭出品してきました。結果は実らない部分もありましたが、十勝地域の酪農家さんから乳牛改良において体型・骨格を評価していただけるような牛づくりができるようになってきました。今年の全日本ホルスタイン共進会出場を目標に来月の十勝、北海道B&Wに向けて飼養管理とショウ準備を全員で一生懸命頑張っていきます。
2025年日本草地学会宮崎大会 高校生研究発表会 優秀賞受賞(取材)について
4月21日(月)、酪農科学科飼料作物分会は2025年日本草地学会宮崎大会の高校生研究発表会において最優秀となる優秀賞を受賞することができました。十勝地域において粗飼料不足や物流の2024年問題等の課題を背景に暖地型作物の飼料適性を検討しました。高校生研究発表会に参加を始め4年目となり、多くの方々に支えられこのような成果を発揮することができています。今年度も研究を継続し、地域に普及するモデルを構築していきます。
除骨実習(酪農科学科)を行いました。
4月18日(金)、酪農科学科養豚分会では約半年、愛情を込めて飼養管理を行ってきた肥育豚を出荷し、枝肉として戻ってきた豚肉を食品科学科のご指導の下、除骨を行いました。人懐っこくいつも元気に駆け寄ってきてくれていた豚の姿を思い出し、家畜として関わり生産していく生産者としての責任を実感しました。
8班の時間外実習(酪農科学科)が始まりました。
4月16日(水)、酪農科学科の1年生8班の時間外実習が始まりました。豚鶏部門では、朝は豚舎の管理、夕方は鶏舎での管理作業を行います。給餌や集卵、畜舎清掃など家畜の管理を通して、畜産の基礎を体系的に学んでいきます。
番組案内(STV)
どさんこワイド179
北海道内の若者に密着取材し、光り輝くであろう原石をとことん応援する
新企画「meijiプレゼンツ 飛べ!Hope」
4月24日(木)放送分
「飛べ!Hope〜酪農家を目指す高校生」で本校の生徒が特集されました。
皆さん、ぜひご覧ください。
酪農科学科・和牛受精卵の採卵・移植技術講習会
6月24日(木)、酪農科学科3年生が和牛受精卵の採卵・移植技術を学ぶ講習会を行いました。とかち繁殖技術研究所の松崎様を講師にお迎えし、採卵プログラムで準備を進めてきた和牛2頭から採卵を実施していただきました。採卵した受精卵は選別後、そのまま乳用牛に移植されました。生徒たちは動物バイオテクノロジー分野の技術を間近で学ぶことができ、貴重な経験となりました。
採草地の枝拾いを行いました。
4月17日(木)、酪農科学科3年生が採草地の枝拾いを実施しました。十勝の春は毎年強い風が吹き荒れます。そのため防風林など森林に囲まれている本校の採草地はいつも風で折れた枝が落ちています。今年度はロータリー前の木が倒れるなど、例年以上の強風が続き、採草地も枝がたくさん落ちていました。生徒たちの懸命な撤去作業によって肥料散布など牧草の管理作業が始まる前に一気に取り組んで片付けることができましたので、今年も良質な牧草が収穫できるよういい天気に恵まれことを願っています。
削蹄実習を行いました。
4月15日(火)、酪農科学科2年生が乳用牛の削蹄実習を行いました。本校では毎年プロの削蹄師にご来校いただき、削蹄講習会を実施していますが、自らの技術を高めるため、削蹄実習も行います。今回は蹄尖部の削蹄を行い、生徒たちも注意点に留意しながら、削蹄に取り組んでいました。
ブタの出荷を行いました(酪農科学科)
4月3日(木)、酪農科学科養豚分会では豚の出荷を行いました。分会活動の中で、飼育環境の比較試験を行いました。屋内とバイオベッドを活用した飼育環境の違いや、地域の未利用資源飼料を活用して飼養管理した豚たちです。今後、肉質などを調査し、有用性について検討します。
ニワトリの搬入を行いました(酪農科学科)
4月3日(木)、酪農科学科ではニワトリの搬入を行いました。120日齢に成長したニワトリを1羽ずつ抱き上げて、ケージに搬入しました。新学期が始まると、1年生の放課後に行われる時間外実習や畜産の授業で生徒の実践的な学びのために活用していきます。
子豚が生まれました(酪農科学科)
4月1日(火)、酪農科学科の豚舎にて、子豚が生まれました。養豚分会の生徒たちで役割分担をして、分娩兆候の見回りや分娩介助、哺乳管理を行いました。遠隔カメラを設置することで2時間おきの見回りなど、春休みのため帰省中である遠方の生徒も分娩に関わることができました。これから約半年、愛情を込め元気に育つように協力して飼養管理を行っていきます。
放送予定(BS放送グリーンチャンネル)
放送日時:4月7日(月)朝7:00~7:30
再放送:4月8日~11日、14日~18日、21日~25日、28日~30日
朝7:00~7:30
内 容:日本農業クラブ 家畜審査競技の特集
本校生徒が取り上げられています。
ぜひ、ご覧ください!
第28回乳牛ジャッジングコンテスト
3月25日(火)、ホルスタインクラブの生徒5名がジャッジングコンテストに参加しました。生徒たちは牛の見方について学び、良い乳牛を見極める力を身につけるため、審査員の解説に耳を傾け、真摯にコンテストに取り組んでいました。高校生団体表彰もいただいたほか、リードの講習にも参加し、乳牛の改良に向け意欲や技術が高まる貴重な時間となりました。
酪農科学科 飼料作物分会 2025年度日本草地学会(宮崎大会)高校生研究発表会
3月18日(火)、酪農科学科飼料作物分会は、宮崎県で開催された2025年度日本草地学会高校生研究発表会に参加してきました。本校を含め、5校から7つのポスター発表がありました。今回の研究内容は、秋播き小麦の後作に緑肥として夏播きされる暖地型作物の飼料利用適性を評価した研究です。粗飼料の確保が喫緊の課題と捉え、励んできたこの研究を多くの専門機関の方々に伝え興味を抱いてもらうことができました。今後も生産者の方々が求めて十勝農業のモデルとなる輪作体系を追求していきます。
牛舎にて実習を行いました
3月13日(木)、食品科学科1年生は畜産の授業で牛の繋留の方法を学びました。ロープワークについて確認した後、実際に牛を繋留しブラッシングを行いました。
牛の除角実習を行いました
3月12日(水)、酪農科学科1年生は畜産の授業で牛の除角実習を行いました。使用道具の名称や、方法を確認しながら実習に取り組みました。
繁殖候補豚を選抜しました
3月12日(水)、2年養豚分会では、繁殖候補豚として雌豚を1頭選抜しました。順調に行けば秋ごろに母豚になる予定です。名前は、養豚分会のメンバーの頭文字を合わせて「ミルキー」と名付けました。繁殖豚としての飼養管理を行い、飼養管理の一連の流れを理解する学習につなげます。
十勝ロイヤルマンガリッツァファームへ農場見学に行きました
3月11日(火)、2年生養豚分会では、株式会社十勝ロイヤルマンガリッツァファーム様へ農場見学に行きました。広々とした放牧地で、はじめて見る色とりどりの巻き毛のマンガリッツァ豚がのびのびと生活する姿に感動しました。マンガリッツァ豚導入までの苦労や、一般の品種とは異なる豚に対応した独自の飼育方法への工夫を聞き、多くの学びを得る機会になりました。
和牛技術研修会に参加しました。
3月12日(水)、酪農科学科1・2年生4名が和牛技術研修会に参加してきました。全国和牛能力共進会北海道大会に向けた候補牛の繁殖が始まるなかで、北海道種雄牛の特徴や十勝和牛が目指す和牛生産の方向性などを学んできました。次年度の共進会参加に向けて学びを深める貴重な機会となり、生徒たちも「理想的な体作りの課題が見えてきた」と自分たちの生産方法について考えを深める機会となりました。今後も定期的に参加しながら和牛生産の質を高めていきたいと思います。
十勝酪農フォーラム2024に参加しました。
3月11日(火)、十勝酪農フォーラム2024に本校酪農科学科乳牛分会の2年生が参加してきました。「暑熱対策を考える~飼養形態別現場実践事例の紹介~」をテーマに十勝管内酪農家の実践事例から暑熱ストレス対策についての意見交換などに参加してきました。暑熱ストレスについて探究活動をしている2年生たちにとってとても学びの多い時間となり、次年度の活動に向けて考える良い機会となりました。
〒080-0834
帯広市稲田町西1線9番地
TEL 代表 0155(48)3051
職員室 0155(48)2102
育成寮 0155(48)2543
FAX 0155(48)3052
E-mail (代表アドレス)
obino-z0@hokkaido-c.ed.jp
このホームページは教育目的で作られたものです。内容や画像の無断引用や転載を禁止します。また、Microsoft Edgeで最適となるように作られています。他のブラウザでは画像の位置や体裁がずれる場合があります。
〇本校校舎前の車両通行について
本校では、生徒の安全確保と交通事故防止のため、次の図のとおりお願いをしております。特に、生徒玄関前は玄関側のみの停車とし、北側は駐停車禁止となります。生徒送迎の際は、なるべく正門より入場するようによろしくお願いします。なお、職員玄関前のロータリーの通行につきましても、時計回りの一方通行となり停車する場合は左側に寄せ、他車が通行できるように配慮も併せてよろしくお願いします。
〇荒天時の対応について掲載しました。下記のpdfをご覧下さい。
荒天時の対応.pdf
〇不審電話にご注意下さい。
卒業生のお宅に、本校学校職員の名をかたり、卒業生の個人情報を聞き出そうとする、不審な電話がかかってくることが多発しています。同窓会員、保護者の皆様におかれましては、被害に遭うことのないようお気をつけください。また、会員名簿等の取扱いに充分ご注意ください。
〇交通規制のお知らせ
交通規制のお知らせ.pdf
楽メ配信・登録についてです。下記のファイルクリックすると閲覧できます。
こちらからスクールガイドをご覧いただけます。