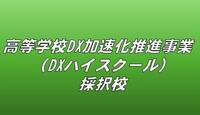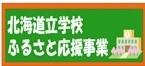カテゴリ:森林科学科
森林科学科 フォークリフト特別教育講習
9月6日、14日、15日の3日間、森林科学科の希望者は「フォークリフトの運転の業務に係る特別教育講習」を受講しました。講習では、座学でフォークリフトの構造や関連法規を、実技では操作技術について熱心に学びました。今回の経験は、進路活動に役立つだけでなく、生徒たちの将来への大きな自信にもつながる、貴重な学びとなりました。
森林科学科3年生 樹名板設置
9月9日(火)、森林科学科3年生の「総合実習」の選択授業で、校舎前の林にある樹名板の修繕と再設置を行いました。春ごろから設置場所の調査や新しい樹名板の制作を続け、ついに完成しました。正門から駐輪場付近までの樹名板を新しくしたので、お近くを通る際はぜひご覧ください。
森林科学科1年生 大収穫!自然の恵みを実感!
9月4日(木)、森林科学科1年生が「農業と環境」の授業で、ポップコーン、ニンジン、ジャガイモの収穫を行いました。先週のエダマメに続き、今回もたくさんの作物を手にすることができ、生徒たちは自然の恵みを肌で感じているようでした。特に自分たちで育てたポップコーンが乾燥して食べられるようになる日を、みんな心待ちにしていました。
森林科学科1年生 帯農大収穫感謝祭
8月30日(土)、森林科学科の生徒はダイイチ稲田店で開催された「帯農大収穫感謝祭」に参加しました。1・2年生はモルックや木札合わせゲーム、3年生は森林ツアーを担当。どのブースも多くのお客様で賑わい、地域の方々と交流する貴重な時間となりました。ダイイチ稲田店様、ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。
第二ひまわり幼稚園交流事業
9月3日(水)、3年生食品科学科の農産加工分会は第二ひまわり幼稚園との交流事業で、いも掘りを行いました。5月に植えたジャガイモが収穫を迎え、子どもたちの元気いっぱいの笑顔に包まれながら、土の中から大きなジャガイモが顔を出すたびに歓声があがり、収穫の喜びを分かち合うことができました。
森林科学科2年生 第3回帯広農業高校スマート林業講座
8月29日(金)、森林科学科2年生の授業で株式会社サトウ様より講師をお招きしてUAVによる森林資源調査について学校林でのフライト実演、CAD室での講義、演習をしていただきました。UAVを使うことで山林調査の時間と労力が大きく軽減されることを実感することができました。
森林科学科1年生 エダマメ収穫
8月26日(火)、森林科学科1年生は農業と環境の授業でエダマメの収穫を行いました。春から大切に育ててきたエダマメ。収穫時期を迎え、大きく実った様子に生徒たちも驚いていました。この日は、各株の豆の量を数える収量調査にも取り組みました。調査を終えたら、採れたてのエダマメをその場で塩ゆでに。みんなで汗を流して収穫したエダマメは、最高においしかったです!
森林科学科1年生 夏季実習
8月4日(月)と21日(木)、森林科学科1年生は「夏季実習」を行いました。背丈ほどの雑草が生い茂る中、生徒たちは柄の長い鎌を巧みに操り、カラマツとミズナラの苗木を丁寧に手入れしました。大変な作業でしたが、友人たちと協力しながら植栽地をきれいにすることができました。実習の帰り道にはカラマツの防風林があり、大自然の中で有意義な時間を過ごしました。生徒たちの努力によって、苗木はすくすくと育っていくことでしょう。
森林科学科2年生 スマート林業講座②
7月9日(水)、森林科学科2年生が「スマート林業講座②」で、西十勝森林組合の村岡昇組合長と白石拓也課長を講師に迎え、機械による下刈りについて学びました。講義では、森林組合の役割や下刈りの軽労化について説明。その後、学校林でハイブリッドラジコン草刈機「神刈」の実演と実習を実施。生徒たちは「神刈」を実際に操作し、その静かな動作音と、パワフルながら簡単な操作で楽に下刈りができることに感動していました。また、空調服の試着も行い、暑い中でも安全で快適に林業の仕事が行える未来に期待を膨らませているようでした。
森林科学科2年生 スマート林業講座①
6月30日(月)、森林科学科2年生がスマート林業の授業で「スマート林業講座①」を実施しました。有限会社大坂林業の中村隆史様らを講師にお招きし、位置誘導装置を使ったコンテナ苗の植え付けを学びました。事前に装置へ入力されたデータをもとに、生徒たちはモニターで植栽位置を確認。マーキング後、筒状の器具で穴を開け、コンテナ苗を植え付けました。参加した生徒からは、「正確かつ楽に作業ができた」や「技術の発展でより効率化に期待したい」と、今後のスマート林業への期待も語られました。
森林科学科1年生 下刈り実習
6月26日(木)、森林科学科1年生は下刈り実習を行いました。下刈りとは植樹した苗木の周りには雑草が生い茂り、苗木の成長を妨げてしまうため、雑草を刈払う作業です。30℃近い気温でしたが、伸びた雑草の中から苗木を見分けることや、間違って苗木を切ってしまわないよう注意をはらい、柄の長い下刈り鎌をうまく使いこなすことに苦戦していましたが、たくさん汗をかきながら集中して実習に取り組みました。
森林科学科1年生 学校林巡検
5月29日(木)、毎年初夏に実施される森林科学科1年生恒例の実習「学校林巡検」が行われました。校地内にある約28haの学校林を歩き、植生の違い、土壌の様子、カラマツやミズナラ植栽地などを2時間ほどかけて見て廻りました。天候にも恵まれ、これまでの先輩が育ててきた森林の様子、森づくりの方針などを直接見て学ぶことができました。第1林班(約13ha)はカシワなど広葉樹林、第2林班(約6ha)はトドマツ、カラマツ、アカエゾマツなどの針葉樹林、第3林班(約9ha)は針葉樹の植栽地やミズナラ植栽地などについて説明を受けました。今後も苗木の植え付け、下刈りなどの保育実習、伐木実習、測量など様々な学習を学校林で行っていきます。
森林科学科2年生 ウド収穫実習
5月27日(火)、森林科学科2年生「特用林産物班」は分会活動の一環で、ウドの収穫を行いました。森林科学科では収穫販売用に山菜を栽培できる専用の畑があり、ウドをはじめギョウジャニンニクやタラノキ(タラの芽)等を栽培しています。ここ数日暖かい日が続き、ウドもグングンと成長!太くて香りのよいものを中心に収穫。収穫量も多く、1袋3本入りで、教職員に販売をしました。山の恵み、四季の恵みでもある山菜。深い味わいに堪能していただければ幸いです。
森林科学科3年生 チェーンソー実習
5月13日(火)、森林科学科3年生はチェーンソー実習を行いました。実習ではチェーンソーの始動・停止の方法を確認し、実際に丸太を用いて玉切りの練習をしました。丸太にチェーンソーの刃を真っ直ぐ入れられず苦戦していましたが、説明やアドバイスをしっかりと聞き、実習に取り組んでいました。実習終了後には「学校林で実際にカラマツを伐倒してみたい!」「伐倒をするには集中力が大切!」と実習を振り返っていました。今後は、伐倒に必要な受け口、追い口の作り方、やすりを用いての目立ての実習を行います。
森林科学科 もくフェスとかちin麦音
5月11日(日)、森林科学科は、満寿屋商店麦音を会場に行われた「もくフェスとかちin麦音(主催:十勝総合振興局林務課)」に、木のものづくり体験ブースを出店しました。森林科学科では、「森の貯金箱つくり」と「木札合わせゲーム」を実施。木札合わせゲームでは、学校林で採集したミズナラやカラマツ、エゾヤマザクラ等の10樹種の木札を制作。神経衰弱ゲームのように同じと思う札をめくると、面にはレーザー加工を施した樹種名があり、当たると木製のキーホルダーをプレゼントしました。天候にも恵まれ、多くの方に体験していただきました。
森林科学科2年生 植え付け実習
5月7日(水)、森林科学科2年生は、専門科目「総合実習」でカラマツ・ミズナラ苗の植え付け実習を行いました。学校林では70年生を超えたカラマツ林を伐採し、人工林の若返りを進めています。森林科学科では苗畑で苗木を育て、それらの木々を学校林で育てることを通して森林づくりの技術を学習しています。カラマツは50年、ミズナラは30年ぐらいで伐採予定と、育成は長期に渡りますが、先輩から受け取ったバトンを後輩に渡しながら学習を進めていきます。
エゾヤマザクラが満開
5月6日(火)、森林科学科が管理をしている生徒玄関前のエゾヤマザクラが満開となりました。一週間ほど前から一輪また一輪と開花し、気温の上昇とともに一気に開花しました。北海道の代表的なサクラであるエゾヤマザクラ。生徒玄関の目の前にあり、この時期が来るとエゾヤマザクラをバックに集合写真を撮るクラスもあります。老木のエゾヤマザクラですが、毎年大輪の花を咲かせてくれることを願って今後も管理をしていきます。
森林科学科 床がえ実習
5月1日(木)、森林科学科1年生は「床がえ実習」を行いました。春は苗木の移植の季節です。苗木を掘り取って他の苗畑に移植し、生育を盛んにし、根の形を整え細根の発生を促し、林地植栽が容易で活着の良好な苗木を育成するために行う実習です。学校林では70年生を超えたカラマツ林を伐採し、人工林の若返りを進めています。森林科学科では苗畑で苗木を育て、それらの木々を学校林で育てることを通して、森林づくりの技術を学習しています。
森林科学科 原木シイタケ栽培植菌実習
4月23日(水)、森林科学科2年生は、原木シイタケ栽培の植菌実習を行いました。栽培に使用する原木は、学校林で育ったミズナラの木を使用しています。ドリルで原木に穴を開け、そこにシイタケの菌糸を含む駒を詰めていきます。植菌を終えた原木は涼しく風通しのよい場所で管理することで、1年後にはおいしいシイタケを発生させることができます。今後も森林資源を活用する技術や知識について学習を進めていきます。
森林科学科 新入生歓迎会
4月17日(水)、森林科学科では1~3年生が一堂に会し、新入生歓迎会を実施しました。2・3年生の代表が各クラスの特色をユーモラスに紹介。新入生の緊張を和らげてくれました。学年対抗で行われたペーパータワー大会では、新聞紙とテープのみを使用し、制限時間内にタワーの高さを競い合いました。先輩たちのタワーは最後に崩れ、1年生が見事勝利。歓声が上がる、賑やかな歓迎会となりました。
〒080-0834
帯広市稲田町西1線9番地
TEL 代表 0155(48)3051
職員室 0155(48)2102
育成寮 0155(48)2543
FAX 0155(48)3052
E-mail (代表アドレス)
obino-z0@hokkaido-c.ed.jp
このホームページは教育目的で作られたものです。内容や画像の無断引用や転載を禁止します。また、Microsoft Edgeで最適となるように作られています。他のブラウザでは画像の位置や体裁がずれる場合があります。
〇本校校舎前の車両通行について
本校では、生徒の安全確保と交通事故防止のため、次の図のとおりお願いをしております。特に、生徒玄関前は玄関側のみの停車とし、北側は駐停車禁止となります。生徒送迎の際は、なるべく正門より入場するようによろしくお願いします。なお、職員玄関前のロータリーの通行につきましても、時計回りの一方通行となり停車する場合は左側に寄せ、他車が通行できるように配慮も併せてよろしくお願いします。
〇荒天時の対応について掲載しました。下記のpdfをご覧下さい。
荒天時の対応.pdf
〇不審電話にご注意下さい。
卒業生のお宅に、本校学校職員の名をかたり、卒業生の個人情報を聞き出そうとする、不審な電話がかかってくることが多発しています。同窓会員、保護者の皆様におかれましては、被害に遭うことのないようお気をつけください。また、会員名簿等の取扱いに充分ご注意ください。
〇交通規制のお知らせ
交通規制のお知らせ.pdf
楽メ配信・登録についてです。下記のファイルクリックすると閲覧できます。
こちらからスクールガイドをご覧いただけます。