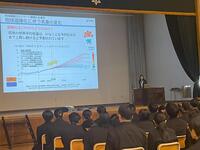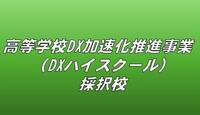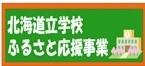2024年11月の記事一覧
商品開発について授業(食品科学科)
11月15日(金)、雪印メグミルク(株)商品開発部の荒井様を招き、商品開発について授業をしていただきました。食品科学科2年生は、商品の開発や企画までの流れについて丁寧な説明を聞き、専門的な知識を学ぶことができました。また、商品開発体験では、グループごとにコーヒー、ミルク、香料の配合比率を変えた飲料を試作し、顧客を想定した商品の開発について考えを深められる良い機会になりました。今後も商品製造についての専門性を磨いていきます。
~帯広農業 柔道部 2024 【帯広工業高校ラグビー部】~
11月16日(土)、帯広工業高校ラグビー部との合同トレーニング会を行いました。毎年のこの時期に、異種目の運動スキルを体験することで、メンタルとフィジカル向上を目指して行っています。両チームから北海道や全国を代表する選手が誕生することを願っています。来年は、新年早々に帯広工業高校ラグビーグラウンドに、お邪魔致します。どうぞ、宜しくお願い致します。
~自分を信じて、仲間を信じて~ 顧問 田中友和
スマート農業プロジェクト特別授業
11月15日(金)、農業科学科・酪農科学科1~3年生はスマート農業プロジェクト特別授業を実施しました。「十勝の大規模畑作で広がるロボットトラクタの取り組み」と題し、帯広畜産大学特任・名誉教授 佐藤禎稔様よりロボットトラクタの実用化に向けての取り組みについてご講義いただきました。実演見学では本校圃場でロボットトラクタが4台同時に作業をする様子を見学し、スマート農業への取り組みについて関心が高まる機会になりました。
農業土木工学科 土質実験がスタート
11月15日(金)、農業土木工学科で土質実験がスタートしました。土質実験では、密度試験、土の液性・塑性限界試験、締固め試験、透水試験、一面せん断試験が行われました。土質実験の目的として、土の強度、透水性を学習するために行われます。実験を通じ、多くの知識、考察力を身につけて欲しいと思います。
ロボットトラクタ4台による馬鈴薯栽培同時無人作業
11月15日(金)、本校圃場でWi-Fi HaLowの長距離通信を利用し、ロボットトラクタによる同時無人作業が行われました。DXハイスクール採択校としてスマート農業を推進する本校がJA帯広川西、帯広畜産大学佐藤禎稔名誉教授、ヤンマーアグリジャパン、NEC様のご協力で実現しました。今後も担い手が直面する課題解決に焦点を当てた授業を展開し、夢の技術の導入が現実となる日を想定できる学びの後押しをしていきます。
森林科学科 第4回スマート林業講座
11月15日(金)、森林科学科は第4回スマート林業講座を行いました。今回の講座テーマは「学校林の林況に基づくゾーニング区分と資源調査」とし、講師として十勝広域森林組合斉藤様、北海道水産林務部成長産業課佐藤様に来校いただき、レーザー機器(LiDAR)や高精度GISハンドヘルド(MobileMapper120)を活用し毎木調査・林分調査を行いました。そこで得たデータを連携ソフトウエアに点群データとして取り込み、樹高や胸高直径、材積に加え地形の情報を効率的に把握することができました。これらの機器を用いることにより森林施業の省力化や森林資源情報の把握・管理の効率化も重要であることを改めて感じる講座でした。次回の講座は最後となる「ICTハーベスタによる生産管理」の予定です。
令和6年度 生徒会・農業クラブ執行部認証式 第5回賞状披露
11月14日(木)、役員選挙で選ばれた、生徒会・農業クラブの執行部の認証式が行われました。新たな帯農のリーダーたちが今後、生徒たちをリードしてくれることを期待します。また、各大会で活躍した生徒たちの賞状が披露されました。これからも帯農生の活躍は続きます。
食品科学科 3年農事見学(雪印メグミルク(株)大樹工場)
11月14日(木)、食品科学科3年生が雪印メグミルク(株)大樹工場を訪問し、見学をしました。さけるチーズの製造ラインでは、機械化が進む中でも人による商品チェックの重要性を学びました。新しくなったカマンベール工場では、7階建て相当の高さがある熟成室に生徒は驚いていました。
食品科学科 3年農事見学(国分北海道(株)道東支社帯広支店)
11月14日(木)、食品科学科3年生が国分北海道(株)道東支社帯広支店を訪問し、物流センターの見学をしました。2班に分かれて「物流に関する授業」と「物流センター内の見学」を行い、卸売(問屋)の役割や意義について学習しました。24時間体制で私たちの生活を支えてくれている物流システムを体験的に学ぶ機会になりました。
食品科学科 3年農事見学(日本甜菜製糖(株)芽室製糖所)
11月14日(木)、食品科学科3年生が日本甜菜製糖(株)芽室製糖所を訪問し、見学をしました。ビートが砂糖になるまでの工程を実際に見ただけではなく、「砂糖をつくっているのはビートであって、砂糖の甘さは自然の甘さです。」という言葉が印象的でした。家でビートを生産している生徒もおり、ビートから砂糖が分離される様子を興味深く見ていました。
スマート農業実証視察会に参加しました。
11月13日(水)、本校農業科学科1年生は帯広市川西農業協同組合様が主催したスマート農業実証視察会に参加しました。ドローンが撮影した画像解析による判定について学び、無人ロボットトラクタが複数台同時に稼働している様子を視察し、生徒たちは様々な農業関連企業のプロフェッショナルに説明を受け、スマート農業の可能性を実感する機会となりました。
農業科学科・酪農科学科「気象庁」様講演会
11月12日(火)、気象庁大気海洋部気候情報課技術主任瀨﨑歩美様をお招きし、「スマート農業に活用可能な気象の知識」をご講演いただきました。詳しく聞く機会の少ない気象と農業、また役立つ気象データの活用法等を丁寧に教えていただき、農業と関係ある気象を深く考え、理解に繋げることができました。
~帯広農業 柔道部 2024 【高校選手権予選】~
11月9日(土)、第47回全国高等学校選手権大会十勝予選大会が開催されました。新チームの始動から3ヶ月。全国へ繋がる予選大会で男子団体試合19連覇を達成し、北海道大会に駒を進めることができました。12月19日(木)~20日(金)に札幌市で開催される北海道大会で練習の成果が発揮できるように更に精進を積み重ねます。大会会場までお越し頂きました柔道部保護者の皆様、関係者の皆様、ありがとうございました。
~自分を信じて、仲間を信じて~ 顧問 田中友和
農業土木工学科 北海道職員業務説明会
11月14日(木)、3~4校時に農業土木工学科で2年生を対象に北海道職員業務説明会が実施されました。説明会では業務内容や福利厚生についての説明をいただきました。また、北海道農業土木職員採用PR動画を視聴するなど大変勉強になりました。この説明会をきっかけに進路実現に向けて頑張ってほしいと思います。
農業土木工学科 実績発表大会
11月13日(水)、4校時において農業土木工学科で実績発表大会が実施されました。5月から分会活動が始まりましたが、いずれの分会も計画的に活動を行っていました。1年生においては、この学科実績発表大会を通じ、来年どの分会に所属し、どのような調査・研究を行いたいか考える良い機会になったと思います。
農業土木工学科 土木材料実験がスタート
11月12日(火)、農業土木工学科で3年生の土木材料実験がスタートしました。実験では、セメントの安定性強さ、骨材のふるいわけ、細骨材の表面水量、スランプなど様々な試験が行われました。12月中旬まで材料実験が行われますが、実験を通じコンクリートの性質について多くのことを学んでくれればと思います。
NHKラジオ マイあさ!で紹介されました
11月11日(月)、NHKラジオ第一で放送されている「マイあさ!」で食品科学科の取り組みが紹介されました。パン甲子園2024に参加した生徒の感想や入試情報についても紹介されています。
https://x.com/nhk_radio_news/status/1855713097841058217
https://www.nhk.or.jp/radio/ondemand/detail.html?p=J8792PY43V_01
上記のリンクから聞き逃し配信があります。是非お聞きください!
農業科学科3学年一斉農事見学実施!!
11月6日(水)、本校農業科学科は3学年一斉の農事見学を行いました。2学年はカルビー北海道工場・KUBOTA AGRI FRONT・株式会社ビコンジャパンの見学をさせていただきました。北海道工場では馬鈴薯の加工工程について学び、AGRI FRONTとビコンジャパンではスマート農業について自動操舵トラクタ等の説明を受けました。
東京食彩フェアに参加しました。
11月3~4日(日~月)、YANMAR TOKYO B1階スクエア会場にて2024年全国農業高校収穫祭令和6年度第19回北海道農業高校「食彩フェア」inTOKYOが開催されました。本校は北海道団の一員として販売会に参加しました。販売当日は多くのお客様に足を運んでいただき、生徒が日頃の実習で手掛ける生産物を多くの方々にPRすることができました。
農業科学科1年生 農事見学
11月6日(水)、農業科学科1年生が農事見学を実施し、ホクレン清水製糖工場、北海道大学を視察させていただきました。ホクレンではビートの加工工程や設備について、北海道大学ではスマート農業技術や経営の観点からご講義をいただき、生徒は積極的に質問をするなど意欲的に取り組んでいました。視察先の皆様には大変お世話になりました。誠にありがとうございました。
〒080-0834
帯広市稲田町西1線9番地
TEL 代表 0155(48)3051
職員室 0155(48)2102
育成寮 0155(48)2543
FAX 0155(48)3052
E-mail (代表アドレス)
obino-z0@hokkaido-c.ed.jp
このホームページは教育目的で作られたものです。内容や画像の無断引用や転載を禁止します。また、Microsoft Edgeで最適となるように作られています。他のブラウザでは画像の位置や体裁がずれる場合があります。
〇本校校舎前の車両通行について
本校では、生徒の安全確保と交通事故防止のため、次の図のとおりお願いをしております。特に、生徒玄関前は玄関側のみの停車とし、北側は駐停車禁止となります。生徒送迎の際は、なるべく正門より入場するようによろしくお願いします。なお、職員玄関前のロータリーの通行につきましても、時計回りの一方通行となり停車する場合は左側に寄せ、他車が通行できるように配慮も併せてよろしくお願いします。
〇荒天時の対応について掲載しました。下記のpdfをご覧下さい。
荒天時の対応.pdf
〇不審電話にご注意下さい。
卒業生のお宅に、本校学校職員の名をかたり、卒業生の個人情報を聞き出そうとする、不審な電話がかかってくることが多発しています。同窓会員、保護者の皆様におかれましては、被害に遭うことのないようお気をつけください。また、会員名簿等の取扱いに充分ご注意ください。
〇交通規制のお知らせ
交通規制のお知らせ.pdf
楽メ配信・登録についてです。下記のファイルクリックすると閲覧できます。
こちらからスクールガイドをご覧いただけます。